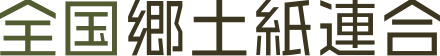苫高専・當摩教授 感染状況の分析を研究 現行解析法の精度向上へ
苫小牧工業高等専門学校の當摩(とうま)栄路教授(62)が、新型コロナウイルスの感染状況を分析する研究に取り組んでいる。現行の基本的な分析方法である「感染症SIR数理モデル」に、マーケティングなどに用いられる「統計的多変量解析法」を追加する研究で、當摩教授は「精度の高い分析ができれば、より効果的な感染症対策につながる」と話す。

新型コロナウイルスの感染者数を予測する「SIRモデル」の応用研究を進める當摩教授
同高専の創造工学科機械系の教授で、地域共同研究センターのセンター長を務める當摩教授はこれまでに新型コロナをテーマにした論文を2本執筆。2月23日に応用数学物理学雑誌の国際誌で英語論文「日本における環境変動の影響を考慮した多変量解析法によるCOVID―19変異型ウイルス感染状況分析の最適推定法」(日本語訳)、今月15日に産業応用工学会論文誌で「感染症SIR数理モデルと多変量解析法を融合したCOVID―19感染状況分析法の新提案」を発表した。
當摩教授によると、現行の感染状況の分析に多く使用されるのは、感染可能性のある感受性人口や感染者数、回復者数から導き出す感染症SIR数理モデル。同モデルを基に「1人の感染者が平均して何人に感染させるか」という実効再生産数を計算しており、数字が高いほど感染の急拡大を意味する。
品質工学や統計学を専門とする當摩教授は、風速や気温、降水量、湿度といった環境的な要因も感染状況に影響しているのではないか―と考え、同モデルに複数の変数から成るデータを統計的に分析できる「統計的多変量解析法」を新たに取り入れた。
1本目の英語論文は昨年4~5月、2本目の論文では昨年9月までの道内の新規感染者数の推移データを使って研究に着手した。
その結果、新型コロナの感染率の推移について、現行モデルでは、拡大も収束も見られない平衡状態となっている期間も見られたが、多変量解析法で分析すると拡大傾向が示されることが判明。感染力の強い変異株の感染拡大で医療機関がひっ迫した状況にあったと推察できるとし、現行の分析だけでは十分ではないことが分かったという。
當摩教授は「今後は人流データやワクチン摂取率といった要因も加えて研究を続けていく」と語った。
関連記事
芽室に新たな観光コンテンツを 食や農業のモニターツアー実施
芽室町の新たな観光コンテンツの構築を目指したモニターツアーが24日、芽室町坂の上の「とかち芽室の百笑farm(ファーム)」で開かれた。町内で農業、飲食、観光業に携わる有志らを中心に企画。知り合い...
酒田港 基地港湾に指定
遊佐町沖、酒田市沖で進む洋上風力発電の事業化に向けて国土交通省は26日、酒田市の酒田港を港湾法に基づく「海洋再生可能エネルギー発電等拠点港湾(基地港湾)」に指定し、酒田港港湾管理者の吉村美栄子県知...
地元の歴史や名所歌う「今昔かるた」 埴生小・中の図書館ボランティアが制作..
「埴生祇園 1100年の古(いにしえ)より」。山陽小野田市埴生地区の歴史や文化、名所を歌った「埴生今昔かるた」が、埴生小・中(東原秀一校長、265人)の玄関奥の大階段に飾られ、児童や生徒たち...
「元気で大きくなって」 ウミガメ放流、児童ら見守る 奄美海洋展示館
鹿児島県奄美市名瀬の奄美海洋展示館は25日、飼育していた6歳のアオウミガメを放流した。2017年夏に大浜海浜公園でふ化後、陸で衰弱していたところを保護された個体。遠足で同館を訪れていた奄美小学...