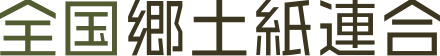幽玄の世界にいざなう まつやま大寒能
約360年の歴史を持つ酒田市の松山能(県指定無形民俗文化財)の「雪の能 まつやま大寒能」が27日、同市の松山城址館で行われ、詰め掛けた能楽ファンらを幽玄の世界にいざなった。
松山能は江戸前期の寛文年間(1661―73年)、江戸勤番の松山藩士が能楽を習ったのが始まりといわれ、明治以降は松山地域の住民による「松諷社」(榎本和介会長)が継承、1980年に県の無形民俗文化財に指定された。大寒能は長らく地域内の總光寺で行っていたが、その後に能楽ファンによる松山能振興会が現名称で復活させ、以来、6月の「花の能 薪能」、8月の「月の能 皇大神社奉納」とともに恒例行事となっている。
この日は、最初に「松山子ども狂言の会」の松山小学校児童10人が子ども狂言「きのこ山伏」を演じ、元気でコミカルな演技に大きな拍手が送られた。その後、松諷社が狂言「盆山」、能「高砂」を上演。このうち、主演目の「高砂」は神をシテ(主人公)にした名作。播磨国(現兵庫県)高砂と摂津国(現大阪府など)住吉の松は相生の松で、その松の精の謡によって夫婦愛と長寿(相老)、天下太平をことほぐめでたい能。後半冒頭でワキ(シテの相手方)の神官たちが謡う「高砂や、この浦舟に帆を上げて―」は、夫婦の理想を示すものとして結婚披露宴でよく謡われてきた。月明かりの中、住吉明神が天下太平などを願って舞うクライマックスのシーンでは、アマチュアカメラマンらが盛んにシャッターを切るなど会場に詰め掛けた人を魅了していた。

住吉明神が舞う「高砂」の一場面
関連記事
霧多布のラッコ 切手に 片岡さん撮影、親子ほのぼの【浜中】
【浜中】霧多布岬周辺に生息する野生のラッコの親子を捉えたオリジナルフレーム切手が、日本郵便北海道支社から発売された。昨年に販売し好評だったことから今年もデザインを変えて販売したもので、今回も...
遅咲き桜とサイロ映える 明治公園でライトアップと投影【根室】
【根室】日本一遅咲きのサクラと赤れんがサイロのライトアップイベントが3日、明治公園で始まった。根室のサクラ開花はまだ先とされるが、初日と2日目はサイロをキャンバスにした初のプロジェクションマ...
井戸尻考古館50周年記念企画展 地元熱意で建館、足跡紹介 長野県富士見町
長野県富士見町の井戸尻考古館建館50周年記念ミニ企画展「井戸尻考古館ができるまで」が同館で開かれている。考古学を愛好した地元住民の熱意で1974(昭和49)年4月30日に開館した井戸尻考古館の歴史...
本州で一番早い夏 白良浜海水浴場で海開き
大型連休の後半が始まった3日は晴天に恵まれ、和歌山県紀南地方の観光地は多くの観光客でにぎわった。白浜町の白良浜では「本州で一番早い夏」と題して海水浴場開きがあり、待ちかねた若者らが海に飛び込ん...