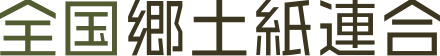吉田城の高石垣に強固な基礎

見つかった「掘り方」(左側)。右側が石垣=豊橋市内で
豊橋市教育委員会文化財センターが吉田城址本丸西側で進めている堀の発掘調査で、城づくりの名人と言われる池田輝政が戦国時代の1590(天正18)年に築いた石垣の基礎が判明した。他に例のない工法で強固に造られ、城郭研究者は、当時、東海一の高さ(11・6メートル)を誇ったとされる「高石垣」を支えていたとみている。同センターは4日、現地説明会を開く。 現場は鉄櫓(くろがねやぐら)と市立豊城中学校の間にある堀で、鉄櫓西側にある石垣の基礎を調査している。石垣は、自然石をほとんど加工せずに積み上げた「野面(のづら)積み」。江戸時代の大地震の際も被害がなく、当時のまま現存する。 調査によると、基礎は、堀底をさらに一段深く掘り下げた「掘り方」を設け、その中に石を混ぜた土を詰めてたたき締めてあり、その跡が何層もあった。 城郭を研究している滋賀県立大学の中井均教授は「深く掘ってコンクリートのようにして石垣が前にせり出すのを防ぎ、崩れ落ちないようにしたのでしょう」と推測。豊川(とよがわ)近くに立地し、砂地の不安定な地盤と、内外に威信を示す高い石垣にすることに対応するため強固な基礎にする必要があったという。 「胴木」と呼ばれる木を置き、その上に石垣を積み上げるのが一般的な工法だが、今回のように胴木のない構造は知られていない。中井教授は「天正18年は、石垣の築き方に試行錯誤だった頃で、その時代の基礎構造が分かった事例として貴重。その頃の石垣が残っているのは基礎がしっかりしていたからではないか」と話している。 4日の現地説明会は午前10時からと午後2時から。調査員が、いずれも一時間半の間に随時説明する。豊橋公園の本丸広場に集合する。
関連記事
マヂラブ・村上さんが新城市観光大使第1号に
新城市は16日、市観光大使の第1号に、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上さん(39)を委嘱した。長篠出身で高校まで市内に住んでいた。 村上さんは市立鳳来中学、県立新城東高校(現新城有教...
キガシラセキレイ飛来 石垣
キガシラセキレイが市内のほ場に渡来した。 体長16・5~18㌢の野鳥で、ロシア中西部やモンゴルなどにかけて繁殖し、冬季は中国南部やインドシナなどへ渡る。日本では旅鳥として少数が渡来し、農耕地や...
高齢者施設の浴室に雄大な富士の絵 秋田公立美大生の池端さん制作
秋田公立美術大4年でグラフィックデザインなどを学ぶ能代市西赤沼の池端咲紀さん(22)が、富士山をテーマにしたデジタル絵画2枚を制作し、同市落合の介護付き有料老人ホーム「サンビレッジ清風のしろ」...
大和証券G子会社 釧路のパプリカ会社に出資【釧路市】
大和証券グループ(本社・東京)の100%子会社、大和フード&アグリ(DFA、本社・同)は、北海道サラダパプリカ(HSP、釧路市大楽毛北2)へ資本参加し、経営に参画した。DFAが運営し生産するパプ...